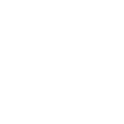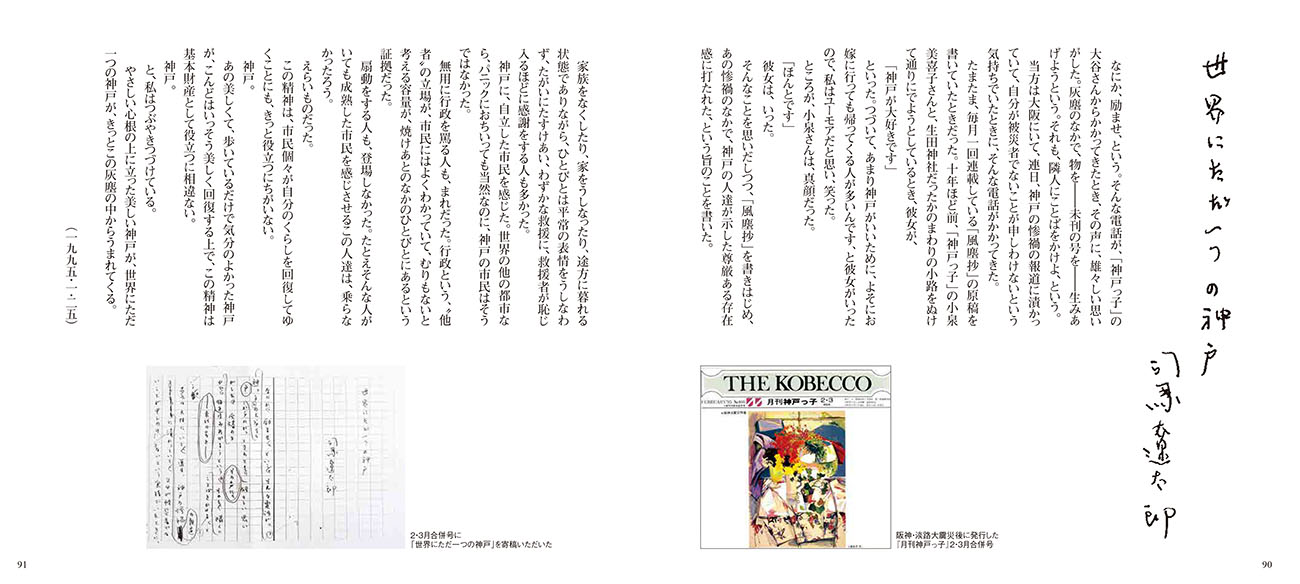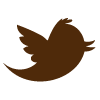神戸の書店や病院の待合室の本棚を眺めてみると、数ある本のなかでひときわ目立つのが四角のタウン誌「月刊神戸っ子」です。
神戸の人なら一目見ただけで「神戸っ子だ」とわかるそのタウン誌の創刊は1961年の3月。この2023年12月号で747号を数えます。

かつては司馬遼太郎さんや小磯良平さんなど、著名な文化人が原稿や表紙を手掛け、現在では東京から神戸に移り住んだ作詞家の松本隆さんの記事を連載するなど、「神戸っ子」のコンテンツは実に多彩。
観光、グルメ、洋菓子、文化、芸術など、他のタウン誌とは一線を画す「神戸っ子」ならではの視点で情報を発信し、読者の支持を集めています。
とはいえ、阪神・淡路大震災やその後の経営難による休刊、そして廃刊の危機を乗り越えてきたことは、あまり知られていません。
1994年に前身の有限会社月刊神戸っ子に入社し、営業・編集を経て現在編集長を務める高橋直人(たかはし・なおと)さんは「司馬遼太郎さんのあの寄稿がなかったら、たぶん続いていない」と言います。
今回は創刊62年の「月刊神戸っ子」の編集長高橋さんと、2019年創刊「KOBEZINE」の安藤編集長による対談です。

服部プロセス株式会社 神戸っ子出版事業部 編集長
高橋直人(たかはし・なおと)
1970年生まれ 神戸在住 1994年前身の有限会社月刊神戸っ子に入社。営業・編集を経て2005年から現体制になり編集長に就任。
神戸の粋人から引き継いだ「神戸っ子」の名
「神戸っ子」のタウン誌としての起源は、1954年から元町商店街で発行されていた「元町」という雑誌でした。「神戸っ子」という名前はすでに1931年に創刊されたタウン誌に使われており、当時は大丸神戸店の社内誌名だったそうです。
「神戸っ子」という名前になった理由は、意外な人からの提案だったと高橋さんは言います。
高橋さん「私も生まれていないときのことで、創業メンバーから聞いた話ですが、当時大丸神戸店の店長だった方が『“元町”だと元町しか紹介ができないだろう。“神戸っ子”という名前をあげるから、もっと神戸を広くPRしたらどうか?』とご提案くださり『神戸っ子』の名前をいただいたそうです。」
かくして「元町」の編集チームは、誌名を「神戸っ子」に、場所を「元町」から「神戸」に広げ、創刊号の発刊にこぎつけます。
創刊号の編集後記には
「三十年前に神戸の粋人が思いをこらして作っていらしたモダンな『神戸っ子』(中略)その名跡を継いで…」 「こうべ『元町』1年にわたって育ててくださった、元町の方にも大変お世話になりました」
との記述があります。
戦前にすでにタウン誌をつくっていた人たちがいたことにも驚きますが、元町だけにとどまらぬよう躊躇うことなく社内誌の名称を譲った大丸の店長さんも「粋人」ですね。
創刊号からはそんな粋人の思いをしっかり受け継いでいこうという気概を垣間見ることができます。

「看板が必要」と司馬遼太郎さんに原稿を依頼
当時創業者の言葉として、高橋さんが伝え聞いていたのが、「看板をつくらんといかん」ということでした。そこで、当時の伝手でちょうど直木賞を受賞した直後の司馬遼太郎さんに原稿を依頼します。
高橋さん「直木賞をとったときの司馬遼太郎さんは37歳。当時どれだけの価値があったかわかりませんが、1万円を持って東大阪のご自宅へ原稿の依頼に伺ったと聞いています。」
賞をとった直後でまだそれほど忙しくなかった司馬遼太郎さんはこの話を引き受けます。
高橋さん「神戸の各所をいろいろまわっていただいて、創刊2号から10回にわたって『ここに神戸がある』という連載を書いていただいたんですね。
後に週刊朝日に『街道をゆく』という連載が1117回にわたって掲載されることになるんですが、その先駆けだったと思います。
それともうひとつ『龍馬がゆく』を書かれる前でもあったので、海軍操練所や生田神社などのゆかりの地を、実際に見て調べたかったんじゃないかということも伺いました。」
司馬遼太郎さんの代表作『街道をゆく』や『龍馬がゆく』のバックボーンにまさか「神戸っ子」の連載があったとは…。意外な相関関係に驚きました。
司馬遼太郎さんと「神戸っ子」の関係は司馬さんの晩年まで続きます。

言葉の凄みを感じた「世界にただ一つの神戸」
1995年1月17日、神戸は阪神・淡路大震災に見舞われます。編集部も被災し、2月号の発刊ができず、3月に2月・3月合併号としてなんとか刊行しました。
この合併号に司馬遼太郎さんは、ある一文を寄稿します。
高橋さん「司馬さんから『これを神戸の人に読んでもらい、励みになれば』と『世界にただ一つの神戸』という原稿をいただいているんです。」
安藤編集長「見せていただいていいですか?(黙読)これは…。ちょっと読んだだけでも泣きそうになりますね。」

高橋さん「神戸に対するエールを送っていただいて。これを号外で発行しました。
この文章を読んだときに、文章の力ってすごいなと思ったんですよ。それから司馬さんの本は全部読んだんです。
実は私は司馬さんが生きているあいだにはお会いしていないんです。というのも司馬さんは震災の翌年に亡くなられたんですね。
亡くなられたときに当時の編集長と一緒に司馬さんのご自宅にうかがったんですが、家が本だらけなんですよ。廊下と居間とかに分厚い本がずらーっと並んでるんですよ。まだご健在だった奥様に訊くと家に2万冊、書庫にあと2万冊あるとおっしゃるんです。
『龍馬がゆく』を書かれたときに『神田の書店の龍馬に関する本がほとんどなくなった』と言われていたくらい、やはりひとつの作品を書かれるのに、それだけの力を注いでらっしゃる。

一方で御仏前を拝見すると菜の花を飾っただけの質素な感じで。あれを見たときに、司馬さんの小説の主人公のような清々しさを感じたんです。 その後、廃刊の危機もあったんですが、こういうものを引き継いでいる本はやっぱり残していきたいなと。司馬さんとの出会いがなかったら、この仕事を続けていないと思います。」
筆者も「世界にただ一つの神戸」を読ませていただきました。いま読んでも胸が熱くなり誇らしい気持ちになります。震災直後に読んでいたら、きっと泣いてしまったでしょう。
ぜひ、以下の画像をクリックしてご覧ください。

錚々たる文化人が誌面に登場
「神戸っ子」には、司馬遼太郎さんのほかにも錚々たる文化人が登場します。
高橋さん「創刊号の表紙は『神戸百景』で有名な版画家・画家の川西英さん、2号目からは洋画家小磯良平さんのデッサン画です。小磯良平さんの作品は40年くらい続きました。
司馬遼太郎さんと大阪外国語大学で一緒だった作家の陳舜臣(ちん・しゅんしん)さんや現在の長田高校のご出身で新開地の近くにお住まいだった映画評論家の淀川長治さん。
諏訪山の異人館に住んでらっしゃったこともある田辺聖子さんや、垂水にお住まいの筒井康隆さんにも寄稿いただきました。
横尾忠則さんはもともと神戸新聞の人なので、本来なら神戸新聞に掲載するのが筋なはずなんですが、必ずみんなが行く方向に行かない方で、『神戸っ子に連載したい』と言っていただいた。
多くの文化人の方にご支援いただいて本を発行してきていることもあって、60年経って時代が変わってもやっぱり我々は神戸が培った『文化』を大事にしていかないといけないなと思っています。」

いち地方都市のタウン誌でありながら、この錚々たる布陣。でもそれは「神戸っ子」の編集部のみなさんが、神戸の「文化」を継承していきたいという想いで発行し続けているからに他なりません。
まさに、地元に愛されるタウン誌の面目躍如と言えます。
「このことはこの人に聞く」が情報源
「神戸っ子」を読んでいると、文化人の寄稿以外にも、通常のタウン誌とはまた違った独自の視点で制作された、実に読み応えのある記事が多く目に付きます。
どのようにして情報を集めてらっしゃるのでしょうか?
高橋さん「『このことはこの人に聞いたらいい』みたいな人が何人かいらっしゃるんですよね。例えばおいしいお店だったら淡路屋の寺本督社長。以前、寺本さんに『カレー食いに行かへんか?』と誘われたので『どこですか?』とうかがったら『コルカタ(インド)』って言われて(笑)。
ああいう方たちって、おいしいものを食べることに労を惜しまないところがあるじゃないですか?そういう人たちに聞くんです。」

安藤編集長「うちも以前、取材いただいています。」
高橋さん「あれは岡力さんというライターさんですね。あの方は一貫樓さんの取材に行って『一貫樓のあんまん』って言うんですよ(笑)。一貫樓って、普通、豚まんでしょ(笑)。岡力さんは「神戸っ子」では取材しないところによく行ってます。そういう面白いスタッフも抱えていて、そういうところからの情報もありますね。」
情報の源はやはり人なんですね。それも情報に精通して突き詰めている人、独自の視点を持っている人。
だから、面白くて読み応えのある記事になるのでしょう。

ストーリーとともに知らない神戸を掘り起こしていく
ここまで高橋さんのお話を聞いていた安藤編集長。ずっと思っていたことがあったようで。
安藤編集長「提案があるんですけど、神戸っ子さん主催で神戸の体験ツアーやったらいいと思うんです。」
高橋さん「実は明日やるんですよ。埋もれている神戸の資産を掘り起こして、それを発信していくという観光庁の事業なんですが、新神戸にある『竹中大工道具館』、あそこが私は素晴らしいと思うんです。というのは、海外の方がめちゃくちゃいらっしゃってるんです。

例えば、昭和初期の大工さんはどれだけの大工道具を持っていたか。のこぎりとかノミとか、179点、全部展示しているんです。
日本は雨が多くて湿度が高く木が柔らかい。それだけ道具があるってことは、木の加工にいろんなことをやってきたからなんですよね。
唐招提寺金堂の三手先組物という釘を使わずに巨木を組み合わせる技法とかを見たら、海外の人は感動すると思うんですよ。
武家茶道の本山とも言える京都・大徳寺の茶室のスケルトンモデルも展示されていて、本来、目に見えない部分の構造も見えるようになっているんです。
お茶室って目に見えないところにものすごく気を配っているわけですから、そういうのを海外の方に見てもらうと面白いんじゃないかと。」

日本人が見ても面白いですよね。
高橋さん「2022年10月号からうちで連載していますが、これらが素晴らしいと思っているからで、素晴らしいものはやっぱり普遍的な価値を持っていると思うんです。普遍的というのは多くの人に共感してもらえる。
ツアーはその後、兵庫県立美術館にある安藤忠雄さんの安藤ギャラリーを見ていただいて、その後に香雪美術館が管理している旧村山家住宅(ふだんは非公開)へ向かいます。
『香雪』というのは朝日新聞の創業者の一人、村山龍平の号で、旧村山家住宅は彼の私邸なのですが、明治の半ばから後半にまだ広大な森だった御影の村に広大な敷地を購入して家を建ててるんです。
『あんな森の中に家建ててアホちゃうか』と言われるんですけど、その後、大阪は東洋のマンチェスターと言われるくらいの工業都市になり、大気汚染などの問題が起こります。そこで、自然環境に恵まれた御影や住吉に多数の財界人が移り住んでくる。
結果、野村財閥の野村徳七や日商岩井の岩井勝次郎、甲南学園をつくった平生釟三郎もそうですね。なのであそこは高級住宅地の原点になったところなんです。
旧村山家住宅には洋館と和館と『玄庵』という茶室があるんですが、国の重要文化財に指定されているんですよ。
ふだんは見学できませんが、特別に入れていただいて、見ていただくんですが、なぜ村山龍平がそこに住んで、茶室を設け、あれだけの美術品を収集したのか、そういうストーリーを知ってもらう機会になります。
神戸の今までになかったものを発信していきたいと思うんです。これっておそらく京都にもないと思うんです。」

安藤編集長「神戸市民も、ほぼほぼ知らないですよね。」
高橋さん「結局、知らないものってまだまだたくさんあると思うんですよね。やっぱり、そういうものを掘り起こしていきたいなと思いますよね。」
筆者は鉄道好きなこともあって、阪急神戸線の御影と岡本のあいだにある旧村山家住宅を避けるように設けられた「村山カーブ」と旧村山家住宅の存在は知っていたものの、中にこれほどの重要文化財があることは知りませんでした。神戸は本当に奥が深いですね。
旧村山家住宅がある御影の香雪美術館は現在長期休館中。所蔵品の一部や洋館居間の一部、原寸大の茶室「玄庵」は、大阪中之島のフェスティバルタワー・ウエストにある「中之島香雪美術館」の常設展示で見ることができます。

自分でブラッシュアップできる神戸人
「神戸の人は自分たちでブラッシュアップしていく力を持っている」。三宮一貫樓が老祥記・四興樓とともに毎年秋に行っている「KOBE豚饅サミット」にもそれが見えると高橋さんは言います。
高橋さん「豚饅サミットを、民間の力だけでやったというのが素晴らしいと私は思うんです。自分たちで考えてブラッシュアップして、いろんな店舗さんとか大学を巻き込んで広げていったというのがいいですよね。
こういう仕事をしてますと、優秀な街の商売人の方々のお話もうかがうんですけど、そのエネルギーってどこから出てくるねんと思うくらい新しいことにチャレンジしていっている。
豚饅サミットはそういう新しいチャレンジから始まって、もう神戸の秋の風物詩になった、という意味ではすごく見習うべきことだと思うんですよね。
震災を経験した東北や熊本からも出店者をお呼びして、社会的な意義もすごく感じますし。
新たなチャレンジから育っていって、規模が大きくなること自体がいいのかはわかりませんけれども、最初の立ち上げ時の思いは大事にし続けてもらいたいなと思います。」
戦前に「神戸っ子」をつくった人たちと同じように、新しくなにかをつくってチャレンジしていく人たちが神戸にいる。戦災や震災で失うものがあっても、そういう人たちが神戸の文化をつないできた。その精神を忘れずにいたいものです。

時代が流れても価値ある記事を
「月刊神戸っ子」は500円で主に神戸の書店で販売されています。しかし、創刊号から最新号まで、一部ない号はあるものの、ほぼすべてをホームページ上で無料で読むことができます。この意図はどこにあるのでしょうか?
高橋さん「知名度を上げていくということと、書店がこれだけ消えていくなかで、これからのあり方を考えていかないといけません。
しっかりした内容が掲載されているので、Webのページビューも増えつづけているんですよね。やっぱり内容ありきだと思うので、そこは大事にしていきたいですね。」
安藤編集長「このあいだ、手にとってしっかり読ませていただいたんですけど、真珠、パン、靴…、これらは神戸を象徴する産業ですよね。スポンサーでもあると思うんですけれども。そこを軸にした記事展開をされていて、売れようと思って書いていないなというのがすごくわかります。」
高橋さん「あくまでも内容重視ではいるんですよね。内容重視だからこそ毎月毎月読んでくださる方がいらっしゃって、クライアントに評価していただける。内容をおろそかにするということはまったくないです。むしろ、価値のある記事を作ることで永続的に見てもらえると思っているので。」

安藤編集長「いい意味で、神戸の読者が読んで心地よい記事を展開されているという印象ですね。売ろうとしてトレンドを追うようになると、すぐにネタも尽きてしまうのではないかと思います。
神戸市民のいち読者として見てすごく面白くて、トレンドを追うのは別の雑誌やムック本とかに任せといたらええやんと。かたや『神戸っ子』はクラシックで、見てて安心する感じなんですけど、読者の層は変遷してきている感じですか?」
高橋さん「年齢層は高いですね。私が53歳なんですけど、私よりも上の方が多いと思います。」
安藤編集長「若い方にも見てほしいというのはあるんですか?」
高橋さん「まだまだフォロワー数は少ないですけど、若い方に向けてインスタをほぼ毎日発信しています。東遊園地のナイトピクニックや六甲山の六甲ミーツ・アートの動画など、本には載せきれない情報を発信をしていきたいと思っています。本誌、Web記事、SNSを有機的に連動させた媒体を創造したいと考えています。」
インスタなどの時代に合わせたツールで発信をすることは、若い層の読者を得るのに確かに有効です。そして、その層が、60年近く続いてきた「神戸っ子」の記事に触れることで、また「神戸っ子」の歴史を今後につないでいく。
そうして神戸の文化が継承されていく、ということなのではないでしょうか。

「KOBEZINE」はまちの人たちにエールを送るメディア
最後に、高橋さんにメディア目線で「KOBEZINE」をどう見ていただいているのかをお聞きしました。
高橋さん「見られるところに出るということで、自分もしっかりやらんとあかんなというのはあると思うんですよ。僕らもこの仕事をしていて思うんですけど、強い信念をもって必死に仕事をされている方の言葉には力があります。取材者である私を含め、人に前を向かせる力といいますか。
また、オープンなところで発言することは自分にプレッシャーをかけることになるので、ちゃんとしなくちゃいけない。まちの人たちにエールを送るという意味ですごくいいと思います。」
同じメディアの先を行く高橋さんからの嬉しいお言葉です。
これからも「KOBEZINE」がまちの人たちにエールを送り続けられるよう、神戸の「人」「こと」「食」を取り上げていきたいと思います。

三宮一貫樓 安藤からひとこと
今回のKOBEZINEいかがでしたか。
神戸メディアの大先輩の胸をお借りしての対談。創刊からの紡いできた歴史の重厚さを聞くにつけ、驚きの内容が満載で、これから「月刊神戸っ子」の誌面を見る目が変わる方も多いのではないでしょうか?
当KOBEZINEも、神戸っ子さんのように長く愛されるメディアでありたいと強く願った次第です。
高橋編集長、貴重なお話をありがとうございました!