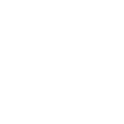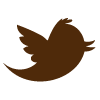神戸の長田に全国からの視察が絶えない多世代型介護サービス付きシェアハウスがあります。その名前は「はっぴーの家ろっけん」。
この場所の最大の特徴が1階のリビングです。
高齢者も子どもも障害のある人も、スタッフや地域の人も、同じリビングで思い思いの時間を過ごす。

一見するとごちゃごちゃしたふつうの家のようですが、その裏側には、首藤義敬(しゅとう・よしひろ)さんが長田というまちで育ち、空き家や介護、子育てと向き合ってきた時間が凝縮されています。
今回のKOBEZINEは「はっぴーの家ろっけん」を立ち上げた首藤さんにお話をうかがいました。

首藤義敬(しゅとう・よしひろ)
1985年生まれ 神戸市長田区出身 株式会社Happy代表
2017年「はっぴーの家ろっけん」を立ち上げる。その後周辺にクライミングジム、カフェなどをつくり、周辺の関係人口の創出に寄与。現在は加古郡播磨町の「はっぴーの家はりま」も運営。
「どっちか」を諦めるのは嫌だった。全部詰め込んだら、この場所ができた
取材当日も1階にあるリビングそしてガレージでは多くの人がそれぞれ思い思いの時間を過ごしていました。
確かに高齢者の施設っぽくはあるけれど、老若男女が入り乱れ、ぱっと見では入居者かどうかもわからない人も多数。奥ではパソコンで作業している人も居るし、電動雀卓を囲んで喋っている人も居る。まさに「ごちゃ混ぜ」。
このリビングやガレージに代表される「はっぴーの家ろっけん」はどういう経緯でできたのでしょうか。

首藤さん「自分の娘がお店出禁になるくらいめちゃくちゃ元気で子育てが大変だったんです。
自分は自営業で仕事が好きなわけではないけど、楽しくやっている。妻は絵描きで絵を描き出したら家事がぶっ飛んじゃう。
子育てもあって、夫婦ふたりともが仕事にのめり込んじゃうとなると『どっちの仕事をセーブしようか』という消極的な話にしかならないですよね。世間的にはそれを『ワークライフバランス』と呼んで、仕事をセーブするという風潮になっていますけど、僕たちはどちらも諦めたくなかった」
仕事と子育ての両立という、多くの現役世代が直面する課題。そこにさらなる難題が降りかかります。

首藤さん「そんなことを考えているうちに、今度はおじいちゃんとおばあちゃんの介護が始まったんです。
介護施設を探してはみたものの病院みたいなところしかなくて、『これは絶対2人に合わへんやろうな…』と思うようなところばっかりで…。
介護も妥協したくないし、子育ても妥協したくないし、もちろん仕事も妥協したくない」
仕事、子育て、そして介護。「どれかを諦める」という選択肢が頭をよぎりそうな状況で、首藤さんはまったく逆の発想に至ります。
首藤さん「そのときに思ったんですよ。『なんで諦めなあかんねん』って。
自分たちがしたい介護、自分たちがしたい子育て、自分たちがしたい仕事の仕方を全部詰め込んだらいいんじゃないか…そう考えてできたのがこの場所なんです」
「諦める」のではなく「全部やる」。そのための器として作られたのが「はっぴーの家ろっけん」でした。首藤さんのその突き抜けた決断が、結果として多くの人を巻き込む場となっていきます。

首藤さん「子育てと介護両方することを『ダブルケア』っていうそうなんですけど、あとあとその言葉を知りました。
今朝もガレージで近所のママさんたちがだんらんしていましたけど、こういった場所が必要なんだと思います。
自分たちの困りごとをシェアハウスにしたら、同じように困っている人たちが集まってきた。そんな感じですね」
「ワークライフバランス」という言葉でバランスを取るのではなく、カオスごと受け入れる。
首藤家の「欲張りなバイタリティ」が形になったからこそ、同じような悩みを抱える人々にとって、ここが切実に求められる居場所になったのかもしれません。



「共感」なんてしなくていい。長田のまちが教えてくれた「港」のあり方
首藤さんは1985年生まれ。この「はっぴーの家ろっけん」がある長田のまちで育ちました。
首藤さん「僕、実は中学くらいから学校に行ってないんですよ。
ずっと学校行って部活やってた人とか、大学まで行ってる人とかって、そこのコミュニティがあったりするじゃないですか。だから今の自分を形成しているものってなんなんだろうって考えたときに、すごく悩んだんです。
中には『メンターっているんですか?』って訊かれたりもするんですけど、自分にとってメンターって誰なんやろって考えたときに、長田のまちの人たちがそうだったのかなと」
学校という閉じた社会ではなく、長田というまちそのものが、首藤少年にとっての教室であり、教科書でした。

首藤さん「先輩後輩という縦の関係性だけではなく、友達にそもそも国籍の違う人も居る。
ちょうど僕が小学校3年生のときに、阪神・淡路大震災があったんですよ。その後の再開発の流れも見てるんです。震災前の街並みの良さも知っている。
親が共働きで忙しくてほとんど家に居なかったから、地域の中で暮らしていたというのもあって、いろんな家に行くんですね。ハウスルールも違うし、長田って韓国の子も多くて『ああ、こういう文化があるんや』って」
震災、復興、そして多文化が入り混じる下町。そこにはきれいごとだけではない、現実の複雑さもありました。
首藤さん「一方で僕らの世代ではなかったですけど、僕らのお父さん、その上のおじいちゃん、おばあちゃんの世代は差別もいっぱいあったというのも聞いてて、そこで傷ついている人がどっちにも居たんですよね。
震災でもまちが復興していくにあたってのいざこざもあった。それもこの目で見てるんです。このまちで育ったことによって、良くも悪くもいろんな文化に触れてきた。
それで気づいたんですけど、そもそも共感する気がないんですよ」
「共感する気がない」。一見冷たくも聞こえるその言葉こそが、首藤さんのたどり着いたリアリズムであり、神戸という街の真髄でもありました。

首藤さん「例えば、僕には在日韓国人の友達もいっぱい居るし、家がヤバそうなところもあるし、逆にめちゃくちゃいい家の子もいる。それが混在しているまちなんですよね。
でもいっぱい居過ぎて、いちいち共感してられない。ただ共存はしてるなと。それがめちゃくちゃ神戸っぽいと思うんです。
神戸のまちの歴史を振り返ったときに、やっぱり港町ということもあって、いろんなものが入ってくる。
港って言ったら物流のイメージがあると思うんですけど、物を介すのは人なんですよ。人の文化が入ってくる。そのことに対して素地があるまちが神戸だと思うんです」
わからないもの、異質なものが、当たり前のようにそこにある。理解しきれなくても、排除せずに隣にいる。

首藤さん「新しいものっていちいち全部理解できないじゃないですか。わからない。でもそういうのが当たり前にあるというのが神戸らしさ。
だから『はっぴーの家』を作ったときの僕のコンセプトは『港』なんです。
神戸が好きな人は気づくんですよ。『ここって神戸らしいよね』って」
「はっぴーの家ろっけん」のコンセプトは「港」。
その言葉を聞いて、この場所の「ごちゃ混ぜ感」がストンと腑に落ちました。無理にひとつになろうとせず、ただそこに在ることを許容し合う空気感。それはまさに、首藤さんが長田のまちで呼吸するように身につけた「神戸らしさ」そのものなのです。

まちの困りごとを「なんとかする」。始まりは妻への「3年待って」から
そもそも首藤さんは「はっぴーの家ろっけん」を立ち上げる前はなにをされていたのでしょうか。
首藤さん「23歳のときから不動産業っぽいことをしていました。自分はサラリーマンに向いてなかったし、なんでもよかったんです。やりたいということもなかった。
当時の長田って震災からの復興もできてるようでできてなくて、道も狭いし、手の入れられない空き家も多かったんです。まちのブランディングもそんなに良くないから、お金かけて改修しても回収ができないみたいなこともあって、不動産屋さんに相談しても解決できない案件がまわりにいっぱいあったんです」
そんな「どうにもならない」状況を前にして、首藤さんは動き出します。

首藤さん「当時結婚したてで、妻に『3年くらい時間ちょうだい』ってお願いをして、困っている大家さんに『じゃあ僕がなんとかしましょう』と。
家の改修が得意な友達を呼んできて、リノベーションして、住む人まで探してあげてたんです。
そしたら大家さんがめちゃくちゃ喜んでくれて。謝礼ももらって『まだあんねん』って次を紹介されて。そういうことをやっていたら『あいつなんとかするぞ』みたいな感じになって、だんだんひとつの業になってきて、いろんな相談を受けるようになったんです」
困りごとを「なんとかする」うちに、それが仕事になっていた。首藤さんが長田のコミュニティの中で頼られる存在になっていく過程は、まさに下町の人情劇のようです。

「なんもできんかった」。ある高齢者との別れが、すべての転機になった
「あいつなんとかするぞ」と周辺の大家さんの信頼を勝ち取っていった首藤さんは、入居者の家賃回収まで任されます。そこで出会ったひとりの高齢者男性との関わりが、大きな転機となりました。
首藤さん「あるときそのリノベーションした物件に住んでいた高齢者の男性が居たんですけど、その人は単身でお酒ばっかり飲んでいて、ちょっとアル中みたいな感じで。その人の家賃回収に行ってたんです。
せっかく月1で会いに行くんだったら楽しみたいじゃないですか。なので業務的な感じではなくて、楽しく雑談しようと思って毎月行っていたら仲良くなったんですね」
単なる回収業務を「楽しみ」に変えてしまうのが首藤さんらしいところです。しかし、そんな関係性にある日、予期せぬ出来事が起きます。

首藤さん「ところがあるときその人が転倒して入院しちゃったんです。帰って来たら車椅子になってしまって、『バリアフリーじゃないからここでは住み続けられへん。住み続けたいから大家に言ってくれ』ってお願いされて。
そしたら当然の話なんですけど、大家さんからは『全然できるけど(お金かかるから)家賃あがるで』と。
でもその人はお金もそんなになかったんで、『もう諦めるわ』と言って施設に行っちゃったんですよ」
住み続けたい人と、貸したい大家さん。どちらの事情もわかるからこそ、首藤さんは無力感に襲われます。
首藤さん「いろんな仕事をしてきましたけど、相談を受けたときにどうしたらいいんかなということを遊びのように提案していくということをして、なんとかしてきたので『あー、なんもできんかったな』とすごいもやもやしたんです。
で、振り返ってみたんですけど、そのおじいちゃん家に、ヘルパーさんが来てたんですよ。『お金ないのに、なんでそんな人いっぱい来てたんやろう』と。
介護保険制度を使ってたんですよね。僕は知らなかったんです」
その「もやもや」と「発見」が結びついたとき、首藤さんの中にひとつの仮説が浮かび上がりました。

首藤さん「それで気づいたんですよね。大家さんがハード面の家とソフト面の暮らしの両方のサポートが同時にできたら、住み続けられたんじゃないか。なんやったら家賃も下げられるんじゃないか。
世の中、新しい建物がどんどん建っていってますけど、そもそもそれ要るのか?それで経済は回ってるのかもしれないけど、数で考えたときに、これ以上つくっても意味はないんじゃないか。
余っている建物を、このおじいちゃんみたいに住み続けたい人が住み続けられる家にしたら、結構いろんな問題が解決するんじゃないかというところが見えて、『これみんな空き家使って暮らしてもらって、サポートしながらやったらいけるんちゃうん?』って思ったんです」
ハード(家)とソフト(介護・生活支援)。縦割りになっていたこの2つをつなぎ合わせれば、諦めなくて済む未来があるかもしれない。この気づきが、「はっぴーの家ろっけん」の構想へとつながり、2017年3月、長田区の六間道商店街に開設されました。

きれいなルートはいらない。「雑菌」のある環境で、子どもは強くなる
首藤さんは「『はっぴーの家ろっけん』は介護施設ではない」と言います。
どういうことなのでしょうか?
首藤さん「僕らのベースが子育てなんですよ。介護施設をやりたいと思ったことは一度もない。やったこともなかったし、行ったこともなかったので、自分の子育ての場所をどこにしたらいいのかなって、めっちゃ考えたんです。
わからなかったので、一般論を調べてみようと思って、世にある育児書全部読んでやろうと思って、本屋さんに行って育児書を買い占めて読んでみたんですけど、だいたい5パターンくらいしかないんですよ。
でもどれもフィットしないんです。たしかに今のことを書いているけど、昔の成長前提の社会構造で書かれてしまっている。今はそういう時代じゃない」
既存の育児論への違和感。これからの時代を生きる子供たちにとって、本当に必要な環境とは何なのか。首藤さんの思考は未来へと向かいます。
首藤さん「自分の子供世代で考えると人口も減るだろうし、大人になってから同じ世代で何かをするってことがまずあまりないだろうなと。なんなら同じ国籍の人と仕事するのも怪しい。
そういう環境で生きていくとなったときに、答えがないことをどうしていくとか、どうやって問いを作るかとか、そっちの能力のほうが大事になると思っていて、そう考えると環境ってめっちゃ大事やなと」

安藤編集長「最近の私の考えでは、大人でもそうですけど、『雑菌性』がないというか。親御さんとかもきれいなルートを子供に歩かせようとする。だから弱いなという思いがあって。でもここは対極にあるなと感じていて、ちっちゃい頃からここで遊ばせといたら強くなるやろなと」
首藤さん「僕が大事にしているのは、『日常の登場人物を増やす』ことだと思っていて、年間200人ぐらいの大人と会えたら面白いなと。
でも、成功者だけの話を聞いても意味ないと思っていて。自分の家庭環境で生きづらさを持っているとか、いろんなしんどさを持っている人もいるような日常の中にいて、そういう人たちに出会うことが大事だと思っています。
家によってハウスルールが違う。同じことをしても怒られる場合もあるし、叱られない場合もある。『これって何が正解?いや、ないねん。人によってちゃうねん』っていうのを、子供の時から体験する。
いろんな理不尽が日常の中にいっぱいあるっていう環境がいいかなって。子供にいかにストレスを与えるかっていうのが必要なんじゃないかと思っています」
あえて「きれいに整えすぎない」環境を用意する。さまざまな年齢、背景、事情を抱えた人が入り混じるこのリビングは、安藤編集長が言う「雑菌性」に満ちています。
「日常の登場人物を増やす」ことで、理不尽や多様な正解に触れる。それは首藤さん自身が長田のまちで揉まれながら育った経験そのものを、次世代に手渡そうとしているようにも見えます。

子供はスターにならなくていい。「お互いがどうでもいい」という心地よさ
いろんな属性の人が集まる「はっぴーの家ろっけん」のリビングでは、通常こういう施設で起こりうることが起こらないと言います。
首藤さん「リビングに居るおじいちゃん、おばあちゃんは僕らに対してなんの興味もないんですよ。普通の施設だったら若い子が来たらスターになるはずなんですが、ならない。
でも今日もそうでしたけど、『一貫楼の豚まんいただいたよ〜』って言ったらその瞬間だけぎゅっとつながったじゃないですか。それでいいんですよ。コミュニケーションめちゃくちゃとることが正解じゃない。共存なんですよね」
ここでもキーワードは「共感なき共存」。過度な期待も干渉もしない関係性が、この場所の心地よさを作っています。

首藤さん「普通のコミュニティって集まるとか集う共感というのがあるけど、ここはそうではない。
瞬間的なものだけではなくて、ずっと続いていく中での出会いと別れがあって、それこそ、まさに『港町』だと思うんですよね。
いろんなものの新陳代謝があると、その寛容性と創造性が生まれやすい。でもそれは共感じゃないんです。
『はっぴーの家ろっけん』の良さはお互いにお互いがどうでもいいというところですね。
それこそいろんな考え方の人が居ますが、けんかにはならないです。二項対立だとけんかになるけど、それ以上になるとけんかにならないんです。
外から見るとリベラルに見えちゃうと思うんですけど、そうじゃない。いろんな考えの人がそのまま共存しているだけなんです」

子供が来ても特別扱いされず、スターにもならない。
それぞれが「自分」のままでいられるからこそ、結果として多様な人が集まり、喧嘩も起きずに回っていく。そんな不思議な調和がここにはあります。
スタッフが「調子に乗れる」仕組みをつくる。AIもソファもそのためにある
さまざまな問題解決をしていく力が求められるのは子供に限った話ではありません。多種多様な人が出入りする「はっぴーの家ろっけん」では、日々さまざまな問題解決能力が求められます。
それは、人じゃないとできない。だから首藤さんは、この業界ではタブーとも言われるAIやロボットのテクノロジーも厭いません。
首藤さん「世間から見たら、この業界の人ってAIとかテクノロジーめっちゃ嫌うんですよ。介護にロボット入れるとかってどうなんって。
僕からしたら大歓迎で、どこよりもコミュニティや地域の連携とかやっている僕らからしたら、機械化することによって、より人間らしいことに集中できる」
人間が人間らしくあるために、テクノロジーを使う。そこで首藤さんが意識しているのが「いかに属人性を上げる仕組みをつくるか」ということです。

首藤さん「普通の人がこの仕組みの中に入ったときに、自分の属人性が爆上がりする仕組みを再現性をもってつくっていくということに専念してます。
僕らがやってる仕事って、その人らしさをいかに引き出すか。それってその人の属人性を上げてあげるっていう行為でもあるわけじゃないですか。でも提供者側の独自性が低かったら、フェアじゃないからできないんですよね。
おいしいものを届けてあげたいというスタッフが居ないと、お客さんにおいしいものを届けられないのと一緒で、パッションがリンクしないとできない」
だからこそ首藤さんは今、スタッフが「どんどん調子に乗れる」状況を意識してつくっています。そのためには、空間の仕掛けにも工夫が必要です。
首藤さん「例えばうちの1階のリビングってやたらとソファが多いんですよ。普通の施設だと転倒のリスクとかもあるので、そんなに置かないんですけど。うちはあえて置いている。 ソファがあると自ずとだらしなさが出る。一気に暮らし感が出るんですね。
それをちゃんと『こういう意図で置いてるんです』と言語化する。そうすると『なるほどね』って伝わっていくじゃないですか。そうなるともう僕を介さないんですよ」
意図を言語化して共有することで、スタッフや利用者が自律的に動けるようになる。
結果として、「はっぴーの家ろっけん」で行われるイベントの95%はスタッフや利用者が勝手に企画し、首藤さんが関わるのはわずか5%だといいます。
「なぜそうするのか」というメッセージが明確だからこそ、みんなが安心して「好き勝手(=自主的)」に動ける。この自由さは、計算された言語化の上に成り立っているのです。

「点」を「円」に。半径15分の景色が変われば、まちは変わる
最後に今後の「はっぴーの家ろっけん」をどうしていくのかを伺いました。
首藤さん「いつもアホみたいな目標を出すようにしてるんですよ。この半径10分、15分以内の空き家を何十件か動かす。なんのエビデンスもないですけど(笑)。
僕がいつも考えていることは、点が円になることしか考えてなくて、『はっぴーの家ろっけん』があったらこのエリアはどうなるか。ほかの場所でもこのエリアはどうなるのかということばかり考えてます」
視点は「点(建物)」から「面(まち)」へ。しかし、画一的な拡大を目指しているわけではありません。
首藤さん「そのまちらしくないと意味がないと思っていて。なにかをするときには、そのまちの長所じゃなくて、弱点もちゃんと探す。それって変えられないので。それがよく見えるやり方ってなんなんだろうって。
だから、まちが1個変わっただけでも変わると思ってるんですよ。1つ筋が違うだけで、カルチャーって変わる。人の通りも来る人も違うし、自分たちの大事なものは出しながらも、そこに気持ちよくフィットするものってなんなんだろうねってことを考えてますね」

首藤さんは「はっぴーの家ろっけん」の周辺に、元々靴屋のビルだった場所をリノベーションしたクライミングジム、100年以上の歴史がある市場を障害者の人たちと一緒にリノベーションして、車椅子の人でも運営できるカフェもつくりました。
なお、2015年には加古郡播磨町に「はっぴーの家はりま」を開設しています。こちらはゆっくりとしたペースで運営しているそうです。そして、それぞれのまちにあわせた歩幅で事業を拡げていっています。
長田のまちで育ち、空き家の相談に乗り、一人の高齢者との出会いに「なんもできんかった」と悔しさを抱き、やがて自分の家庭のカオスをまるごと詰め込んでできた「はっぴーの家ろっけん」。
そこには、神戸という港町が長年培ってきた「共感なき共存」「わからないまま一緒にいる」という文化が色濃く流れています。
きれいに整えられた施設ではなく、ソファがやたら多く、暮らしの痕跡がそのまま残るリビング。 そこはまさに、モノではなく「人と文化が行き交う港」です。首藤さんが目指しているのは、制度や福祉の“正解”をきれいに並べた場所ではなく、「人の営みが見える港」 なのかもしれません。
そして、その港はやはり神戸というまちだからこそ、生まれたのだと感じる風景でした。

三宮一貫樓 安藤からひとこと
今回のKOBEZINEいかがでしたか?
過去2回は「海」「空」と来て、
今回のテーマは「人」まさに神戸を象徴するような並びになり感慨ひとしおです。
さて、首藤さんのお話しは本当にパワフルで面白い!
取材当日も時間を忘れて話し込んだ記憶があります。
子供の時にここがあれば通いたかった。
今、ここのリビングで酒を飲みながらはべりたい。
爺さんになったら居住者となり、ここで朽ち果ててみたい。
そんな気持ちに自然とさせるのは首藤さんの人となりと、はっぴーの家の空気に他なりません。
本当の美しさとはなんだ?
こんな命題も自然と湧いてきました。
その答えはきっとこの家の空気に触れると導きだされることと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。